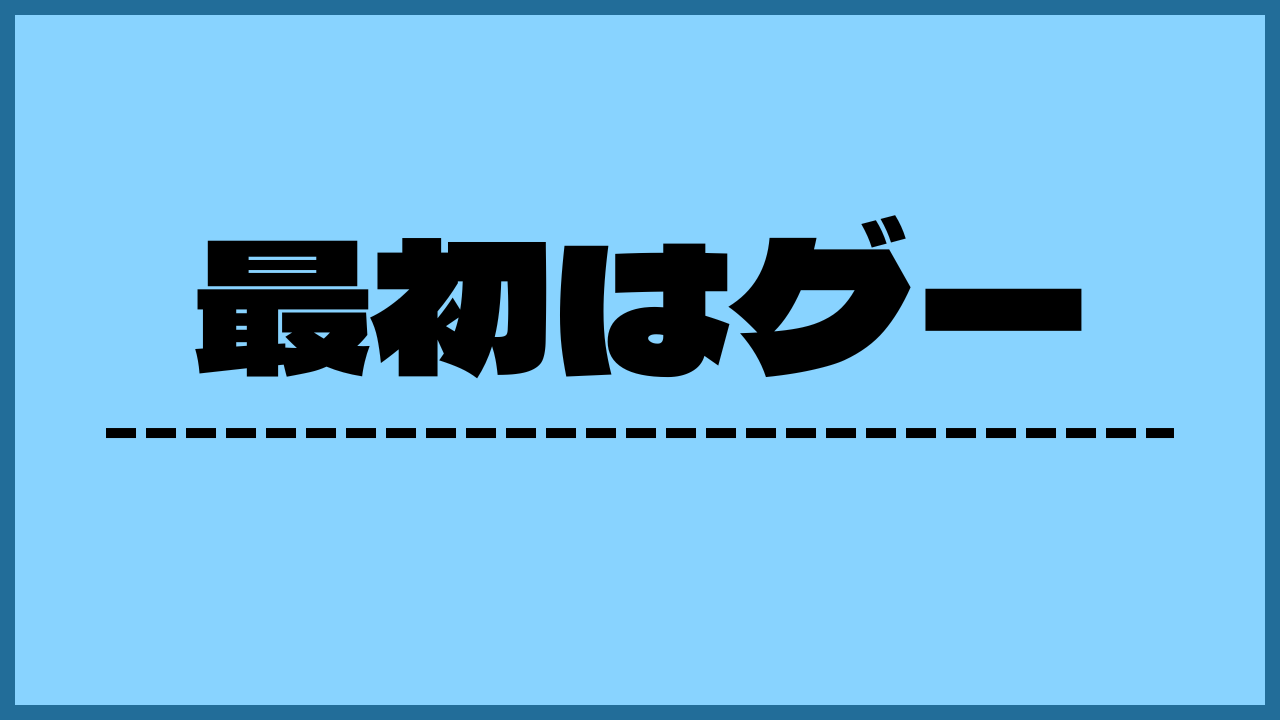「最初はグー」、このお馴染みの掛け声がどこから生まれたのか気になったことはありませんか?
実はこのフレーズには、志村けんのエピソードから芸者の遊び、そして野球拳まで、いくつかの興味深い起源説があるのです。
さらに、日本だけでなく世界各地で異なる掛け声や独自のじゃんけん文化が発展しており、地域ごとの工夫やユニークな要素がたくさん!
この記事では、「最初はグー」のルーツを探りながら、じゃんけんの多様性や魅力をたっぷりご紹介します。
「最初はグー」の元ネタとは?
「最初はグー」の元ネタについては、以下の3つの説があると言われています。
- 志村けんの発案説
- 芸者の遊び説
- 野球拳起源説
どれも近そうで遠そうな節になっています。
では、それぞれの説に関して詳しく見ていきましょう!
志村けんの発案説
最も広く知られているのは、お笑い芸人の志村けんが発案したという説です。1969年から1985年まで放送されたTBS系列の人気番組「8時だョ!全員集合」の収録後の飲み会がきっかけとされています。
酔っぱらった出演者やスタッフがじゃんけんのタイミングを合わせられず、志村が「最初はグーだよ」と提案したことが始まりだとされています。
芸者の遊び説
一方で、志村けんが「最初はグー」を使う以前から、東京・神楽坂などのお座敷で芸者たちがお遊びで使っていたという説もあります。
志村たちがこれを見て、仲間内で使うようになり、後にコントで採用したという可能性が指摘されています。
野球拳起源説
さらに遡ると、「最初はグー」の起源は本家野球拳にあるという説もあります。本来の野球拳では、「アウト!セーフ!よよいのよい!ジャンケンぽん!」というかけ声で「よよいのよい!」のタイミングでグーを出すというルールがありました。
この「よよいのよい!」が「最初はグー!」に変化した可能性が考えられています。
これらの説は互いに矛盾するものではなく、芸者の遊びや野球拳が元になり、志村けんがテレビで使用したことで全国的に広まったという流れも考えられます。
いずれにせよ、「最初はグー」が日本のじゃんけん文化に大きな影響を与え、現在では当たり前のように使われているフレーズとなっていることは間違いありません。
他の掛け声
「最初はグー」以外にも、じゃんけんの掛け声には様々なバリエーションや変わり種があります。以下にいくつかの例を紹介します。
地域による違い
地域によって異なる掛け声が使われることがあります:
- 「インジャン、ホイ」「インジャン、ポイ」:主に西日本(京都、大阪、兵庫など)で使用
- 「ジッケッタッ」「チッケッタッ」:東北や関東地方で見られる
- 「ほうらいき」:東北地方
- 「いんじゃんほい」:関西地方
ユニークな掛け声
子どもたちの間で生まれた面白い掛け声もあります:
- 「ジャンケンジャガイモサツマイモ」
- 「ジャンケンもってスッチャンホイ」
- 「ヤイヤ、オー」「ヨーエッキ」「ユイヤー、エス」
長めの掛け声
より複雑で長い掛け声も存在します:
- 「最初はグーまたまたグーいかりや長介頭はパー正義が勝つとは限らないじゃんけんポリポリカトちゃんぺみんなでキャイーンでジャンケンホイ」
- 「最初はグーぐっぐっぐっぐ 目ー何個こっこっこっこっ 恋してるるっるっるっるっ るんぱっぱぱっぱっぱっぱっ パンツ何枚普通」
「ポン」の変化形
「ジャンケン、ポン」の「ポン」部分にもバリエーションがあります:
- 「ジャンケン、エッ」「ジャンケン、キッ」「ジャンケン、サイ」
- 「ジャンケン、シッ」「ジャンケン、ショ」「ジャンケン、チッ」
これらの多様な掛け声は、地域の文化や子どもたちの創造性を反映しており、じゃんけんという単純な遊びに豊かな表現をもたらしています。
海外のじゃんけん
「海外でのじゃんけん」は、基本ルールは共通しながらも文化ごとに独自の進化を遂げています。
主要な特徴を地域別に整理してみましょう。
基本ルールの国際的共通点
- 3つの手形(グー・チョキ・パーに相当)で勝敗を決める
- 勝敗判定:
Rock crushes scissors(岩がはさみを壊す)
Scissors cut paper(はさみが紙を切る)
Paper covers rock(紙が岩を包む)
地域別の呼称と特徴
東アジア
- 中国:
「石头剪刀布(シートウジエンダオブー)」
手の形:拳(石)、Vサイン(はさみ)、平手(布) - 韓国:
「가위바위보(カウィバウィボ)」
順番が「はさみ・岩・布」と逆
欧米諸国
- アメリカ/イギリス:
「Rock-Paper-Scissors」
ビジネス現場でも使用(例:2005年日本の企業が競売業者選定に採用) - ドイツ:
「Schnick Schnack Schnuck」
4つ目の手「井戸」を追加(水が岩を沈め、紙を濡らす) - フランス:
「Pierre-Papier-Ciseaux」
地域によって「Feuille-Caillou-Ciseaux(葉・石・はさみ)」とも
その他の地域
- フィリピン:
「Jack-en-poy」
歌を歌いながら行う長いバージョンが存在 - ブラジル:
「Pedra-Papel-Tesoura」
じゃんけんに加え「ラグビー拳」と呼ばれる独自バリエーション - エジプト:
ラマダン期間中に「アアク」と呼ばれる戦略ゲームとして発展
文化的な差異
- 手の形の解釈:
マレーシアではパーを「水」、チョキを「鳥のくちばし」と表現 - 使用場面:
日本ではビジネス決済にも使用されるが、ベトナムでは子供の遊びと認識 - 地域特性:
モンゴルの「ポーガルガッフ」では馬の動きを模した独自ルール
国際大会の進化
- World RPS Society:
2002年から世界選手権を開催 - 新ルール:
「ウォーター(水)」を追加した4択バージョンが考案 - 戦略:
統計的に男性は岩を35.4%、女性ははさみを29.6%多用
日本の「じゃんけん文化」が世界に与えた影響は大きく、特にビジネスシーンでの活用や競技化の動きは「Jan-Ken-Pon」として国際的に認知されています。
一方で、フランスの「井戸」追加やドイツの「クマ・狩人・銃」バリエーションのように、各地でローカルルールが生まれ続けている点が特徴的です。
まとめ
「最初はグー」の起源については、いくつかの興味深い説がありましたね。以下におさらいしてみましょう!
- 起源説:
- 志村けんの発案説:
「8時だョ!全員集合」の飲み会がきっかけ。 - 芸者の遊び説:
芸者文化から派生した説。 - 野球拳起源説:
野球拳の「よよいのよい!」が原型。
- 志村けんの発案説:
- 地域別掛け声の特徴:
- 西日本:インジャン、ホイ
- 東北:ほうらいき
- 子どものユニークな掛け声例も多々。
- 海外のじゃんけん:
- 中国や韓国など東アジアでも同様の遊び。
- 欧米ではビジネスにも活用。
- 地域独自のバリエーションが豊富。
- 競技化:
- 世界選手権を開催する「World RPS Society」。
- 新ルールや戦略の研究も進行中。
「最初はグー」が生まれた背景に加え、地域や文化ごとの広がりを見ると、じゃんけんが単なる遊び以上の存在であることがわかりますね。
ぜひ身近な文化や国際的な違いも楽しみながら、日常で活用してみてください!