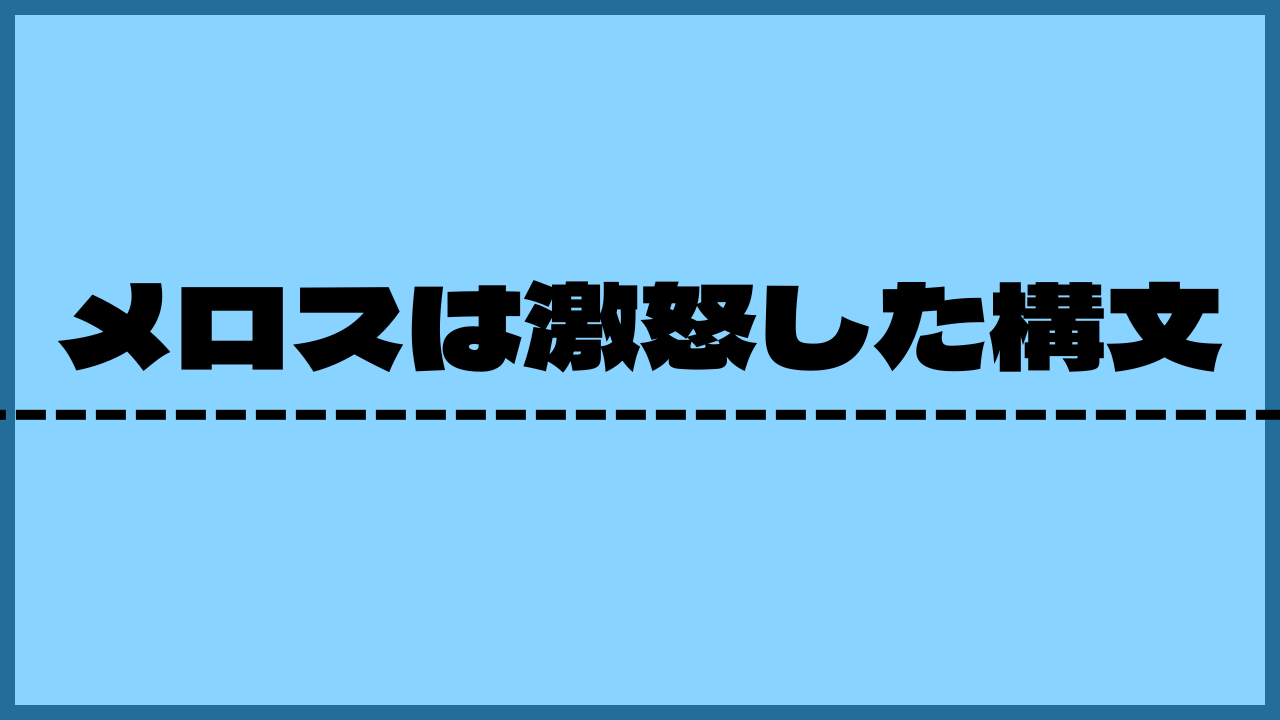「メロスは激怒した構文」という言葉を聞いたことはありますか?
インターネット上で見かけることが多いこの表現、実は太宰治の名作『走れメロス』から生まれた言葉なんです。
最近では、SNSやネット掲示板で、様々なパロディとして楽しまれています。
この記事では、「メロスは激怒した構文」の元ネタや特徴、そして現代的なアレンジの仕方まで、具体的な例文を交えながらわかりやすく解説していきます。
太宰治の名作がどのようにしてネットミームとなり、新しい表現として進化していったのか、一緒に見ていきましょう。
「メロスは激怒した構文」の元ネタ
「メロスは激怒した構文」の元ネタは、太宰治の短編小説『走れメロス』の冒頭部分です。
この構文は物語の書き出しとして非常に印象的で、主人公メロスの感情や背景を簡潔に描写する特徴があります。
冒頭の文章は以下の通りです。
「メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。
メロスには政治がわからぬ。
メロスは、村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らして来た。
けれども邪悪に対しては、人一倍に敏感であった」
この構文はその後インターネット上でミーム化され、多くのパロディや派生作品が生まれました。
例えば、「メロス」を別のキャラクター名に置き換えたり、現代的な設定を加えたりすることで、多様なユーモア表現が展開されています。
メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐のいかがなものか言いたいマンを除かなければならぬと決意した。メロスには社内政治がわからぬ。メロスは、村のサラリーマンである。笛を吹き、羊と遊んで暮らして来た。けれども邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。
— SHARP シャープ株式会社 (@SHARP_JP) August 18, 2020
「メロスは激怒した構文」は、太宰治の小説『走れメロス』の冒頭部分から派生した表現で、特にインターネット上で多くのパロディが作られています。
メロスは激怒した構文の使い方
「メロスは激怒した構文」は、以下のような流れで構成されます:
- 主語の感情表現: 「[主語]は激怒した」と始まる。
- 決意表明: 「必ず、かの[対象]を除かなければならぬと決意した」と続く。
- 無知さの提示: 「[主語]には[理解できないこと]がわからぬ」と述べる。
- 素性の説明: 「[主語]は、[職業や立場]である」と続ける。
- 過去の生活描写: 「[活動内容]をして暮らしてきた」と描写する。
- 矛盾する性質: 「けれども[対象]に対しては、人一倍に敏感であった」と締めくくる。
このテンプレートを使うことで、さまざまな状況やキャラクターに応じたパロディが作成できます。
具体的な例文
ゲーマー版
メロスにはゲームの攻略がわからぬ。
メロスは、村の初心者プレイヤーである。
コントローラーを握り、NPCと会話して暮らして来た。
けれどもチート行為に対しては、人一倍に敏感であった。
SNS中毒版
メロスにはデジタルデトックスがわからぬ。メロスは、村のインフルエンサーである。
いいねを押し、フォロワーと遊んで暮らして来た。
けれどもフェイクニュースに対しては、人一倍に敏感であった。
料理初心者版
メロスには調理法がわからぬ。メロスは、村の食べるだけ担当である。
レトルト食品を温め、出前と遊んで暮らして来た。
けれども食中毒に対しては、人一倍に敏感であった。
これらの例文では、元ネタとなる『走れメロス』の構造を保ちながら、異なるテーマや状況に応じて内容が変更されています。このように「メロスは激怒した構文」を利用することで、ユーモアや皮肉を交えた表現が可能になります。
まとめ
「メロスは激怒した構文」は、太宰治の『走れメロス』から生まれた表現方法についてご紹介しました。
最後に、この記事の重要なポイントをおさらいしていきましょう。
- 元ネタと特徴:
- 『走れメロス』の印象的な冒頭文
- 6つの要素(感情表現→決意表明→無知さ→素性→生活→矛盾)で構成
- 現代での活用:
- SNSやネット掲示板でパロディとして人気
- ゲーム、SNS、料理など様々な場面で応用可能
この構文は、様々な状況に当てはめやすく、読み手の共感を得やすい表現方法として親しまれています。
皆さんも身近な出来事やテーマで、オリジナルの「メロスは激怒した構文」を作ってみてはいかがでしょうか。